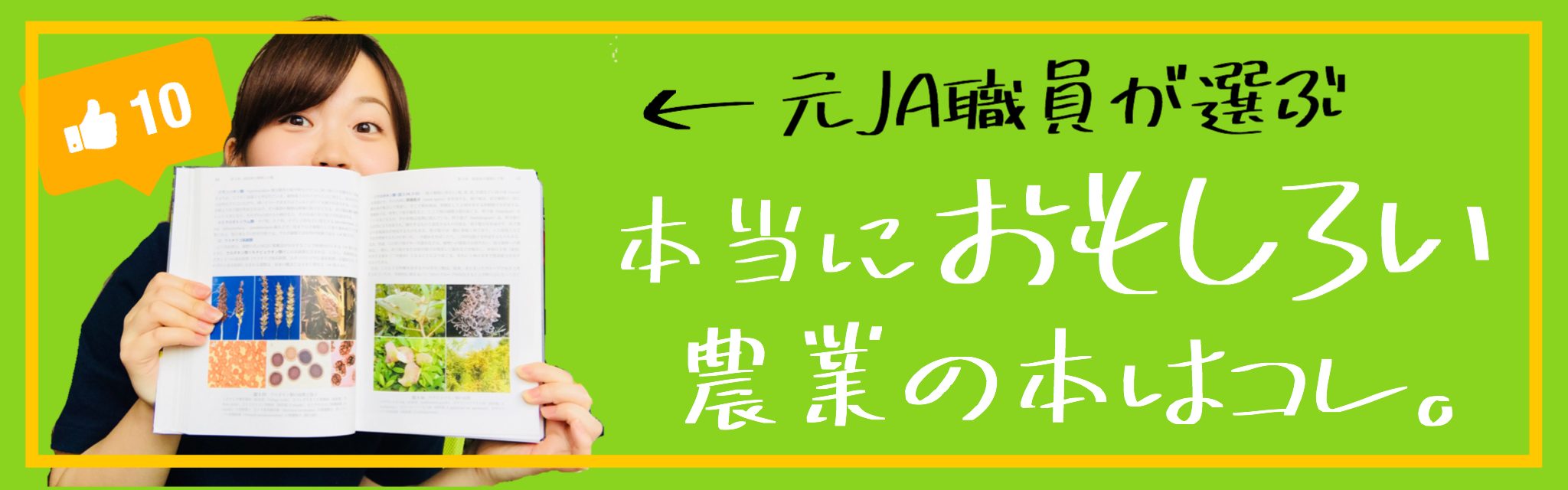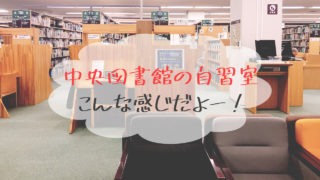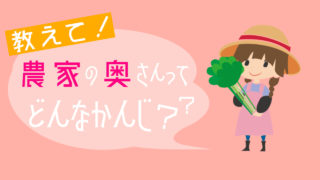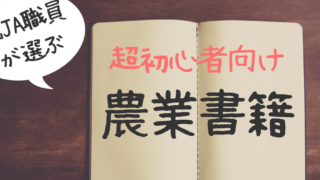こんにちはゆかたん(@AgriBloger)です。
あけましたね、平成ラスト数ヶ月ーーー!!!ことよろでございます。
昨年の暮れ、農家のおばちゃんの恒例行事である「餅つき」に参加してきました!!
今の時代に杵と臼で餅をつく文化ってどれくらい残っているんだろうと気になったんですよ。
今は自動の餅つき機を使う家庭が増えたと思うんですが、祖母の家では私が生まれる前から今でも杵と臼で餅つきをしています。
わたしが今回行ったのは、餅つきが見られるのは祖母の代でもしかしたら最後になるかもしれないと思ったからです。
「残さなきゃ!」と本能的に思ったというか。やらなきゃ後悔しそうだなと。
いつかこの文化がなくなったときに、振り返る瞬間が来るんじゃないかと思ったんです。
で、多分その瞬間はくるような気がしてる。人生で食べた餅は90%くらい祖母のものだと思います。舌が覚えているわけで。
実際はお手伝いより撮影がメインになったんですがw、とてもいい写真が撮れました。まじで。ほんと。(しつこ)
今回はお米の段階からラップに包むまでの写真をまんぷくになるまで公開します!!
餅つきって意外と手間かかってんねんな、ってことを知るいい機会になったのでよかったら見ていってくださいな。てか見て。
平成最後の餅つきですよ!!!(なんでも平成最後とかいう)
※写真の無断転用は禁止です。
餅つきの前の準備
餅をつく前にもち米の準備からはじめますからね。餅つきの前にもち米を待って水気を切っておいたものからスタート。

お米は外の倉庫にある薪ストーブ炊きます。餅つきに使うお湯も一緒に沸かしておきます。
結構すぐ炊けるので、次から次へと炊いては餅ついての繰り返しでした。

祖母が小豆を栽培していたときは、自家製の小豆であんこを作っていましたね〜。最高。
このあんこなんですけど、全然甘くなくてあんこだけでも食べれるくらいおいしいです。
大きい鍋で作ってるので余った分は持ち帰り!おしるこにできるからね。




もちつきの開始!
今回餅つきは5、6回やったかな。我が家では、鏡餅とのし餅と大福餅と豆餅と豆大福の5種を作っています。(忙しい)
第1・2ラウンド 鏡餅・のし餅
最初に鏡餅とのし餅(切り餅)を作っていきますよ〜。
餅をつくのはおじさんで、合いの手を入れるのがおばあちゃんです。炊けたお米を急いで臼に移して、ごはんを杵でつぶしていきます。


お米が潰れたら、餅になるまでついていきますよ!!
母が子供の時に住んでいた方の家で餅つきはするんですけど、振動がすごくて地震がきたかと思ったw





意外とお米を入れたら10分くらい?でお餅が出来るんですね!
急いで木の板の上に移して、鏡餅から作っていきます。
できたお餅をアツアツのうちに少しずつお餅をちぎっていきます。絶対あついよね・・・猫手のわたしにゃ到底できなさそう・・・
湯気がすごいのは、この部屋が古い上に寒波のせいでものすごい寒かったからですw



で、母と祖母がそのちぎったお餅を丸めて鏡餅になるように丸めていきます。
祖母はコロコロコロ〜っと簡単に丸めるんですけど、すごく綺麗。手際悪いと形が悪いまま冷めちゃうこともありますからね。


祖母の家ではお供えする場所が多いので、鏡もちは10セットくらい作ったかな。ちょっと小さめの鏡餅です。
余ったお餅はのし餅にするので、麺棒で均等な厚さになるように伸ばしていきます。
結構力が入るみたいですね。均等に伸ばさないと餅の厚さが変わってしまうので、大変なようです(やってないけど)。



ここからまた何回か餅つきをして、のし餅が完成したら、暖房のないお部屋で冷ましておきます。

第3・4ラウンド 大福もち
次に大福餅を作っていきますよ!!!
鏡餅と違って大福餅はよりついて柔らかくしていきます。
おもちを持ったら手から滑り落ちるぐらいまで柔らかくしていくんです。
ちぎったお餅をうすーく伸ばして、先ほど作っておいたあんこ玉を包んで形を整えったら大福の完成。

できあがったばかりの大福を食べたんですけど、お餅がすっごく柔らかくて本当に美味しかった。とろけるお餅。普通に2個くらい食べれるレベル。

わたしもいいだけ写真を撮ったあとに大福を包むの手伝いました。(全然手伝わないじゃんと母に愚痴られながら)
前回手伝ったのは記憶にないぐらい前だし、不格好の大福が爆誕しましたよ、ええ。
意外と簡単そうに見えるんですが、おしりの部分をきれいに包むのが難しいんですよね。あんこも大福の中心になるように包まないとだめだし。
大福はできたらラップに包んで完成です。
ラストに豆餅!
大福までできたので最後に豆餅を作っていきます!!!
豆餅は黒豆をもち米に混ぜて作るんですけど、ちょっと塩気が効いてて美味しいんですよね。

粒の大きい黒豆がごろごろ入っています。おもちができたら楕円に整えて冷ましておきます。
こうやって作ってたんか・・・(今更)

去年から豆餅を使って豆大福を作りはじめたんですよ。この豆大福がすごくおいしいんですけど、今回餅の配分を間違えたそうで1人1個しか当たりませんでしたw 残念w
出来立ての豆大福ものすごくおいしかったなあ。来年また食べたい。大量に。


のし餅が冷めたら切って完成!
餅つきが終わったらのし餅を切っていきます。
冷ましておいたのし餅を長方形の大きさになるように切り分けます。


切ったお餅をラップに包んで完成です。

我が家ではお正月に食べるお雑煮から、冬休みのおやつに子供の時から食べていました。
大福は1日1個食べれるぐらいおいしいんですよね〜。トースターで焼くとちょっと香ばしく、あたたかいのでおすすめ。
暮らしの写真を残したい

以上、我が家の餅つき写真でした。
今回餅つきの写真をはじめて撮ったんですけど、撮れ高すごくないですか。
自分で言うのも何なんですけど、めっちゃよく撮れたなあと。
SNSで公開したら結構コメントもらってうれしかった(ツイッターやインスタはコラージュしたのを載せてます)。ありがとうございます。
おばあちゃん家の餅つきシリーズ第2弾
(インスタストーリーズより) pic.twitter.com/a3eLAr16ke— ゆかたん|農業女子ブロガー (@AgriBloger) 2018年12月29日
すごいエモくて泣きそうになりながら現像してました。
そんな折にラブグラフのこまげさんがこんなこと言ってたんですよね▼
「インスタ映え」と「エモい写真」は別物だと写真の会社をやっていて思う。
インスタ映えは写真として綺麗さにフォーカスするのに対して、
エモい写真は背景のストーリーにフォーカスする。目に見えるものに価値を見出すものがインスタ映え。
目に見えないものに価値を見出すものがエモい写真。 pic.twitter.com/3gz7fE19AY— こまげ(ラブグラフ代表) (@komage1007) 2018年11月29日
わたしはエモいを通り越して泣けたけど、きっと赤の他人はそうではないんだろうと思ってたので、腑に落ちました。
これらの写真は自分の目にしか見えないものがたくさん映っているんです。
家の文化を大人になってから写真という形に残せたことの喜びとか、撮りながらいつの間にか大人になっていたことに気づいた儚さとか、言葉にできない感情がつまってる。
祖母の前ではいつまでも子どもだと思っていたら、どうやら違うらしい。
そういうのをきっとエモいというんだろうけど。
はじめて自分の家の文化を写真に残したんですが、結果的によかったなと思います。
まあ家族に見せてないんですけどね!!これから見せよう。
実は餅つきの後、北海道の郷土料理の「飯寿司」を樽からより分ける作業もしました。
年の瀬っておばあちゃんこんなに忙しかったんだってはじめて知りましたよ。
(飯寿司の記事はまた別の機会に書くかも)
いつも食べるだけだったし、こんな苦労があっておいしい祖母の料理を食べてたんやなと。
今年はこうやって暮らしの写真をもっと撮りたいんですよね。
何年も続く文化を写真に残すことは、後世を生きる人間が「昔こういうこともあったよね」って明るく振り返れる大切なツールになると思うんです。
長々と書いてしまいましたけど、今年もゆかたん農学校をよろしくお願いいたします。
したっけね!